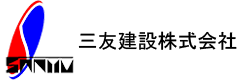子安町 基礎の配筋工事
取材現場【No.03八王子市 商業施設】
鉄骨造(S造)
現場取材:2回目
前回の記事はこちらhttps://www.sanyu-kensetsu.co.jp/2025/07/25/koyasutyou-1/
前回、解体・根伐工事が完了した現場では
捨てコンクリート打設後に墨出しをして、基礎ピットの配筋工事が行われていました。
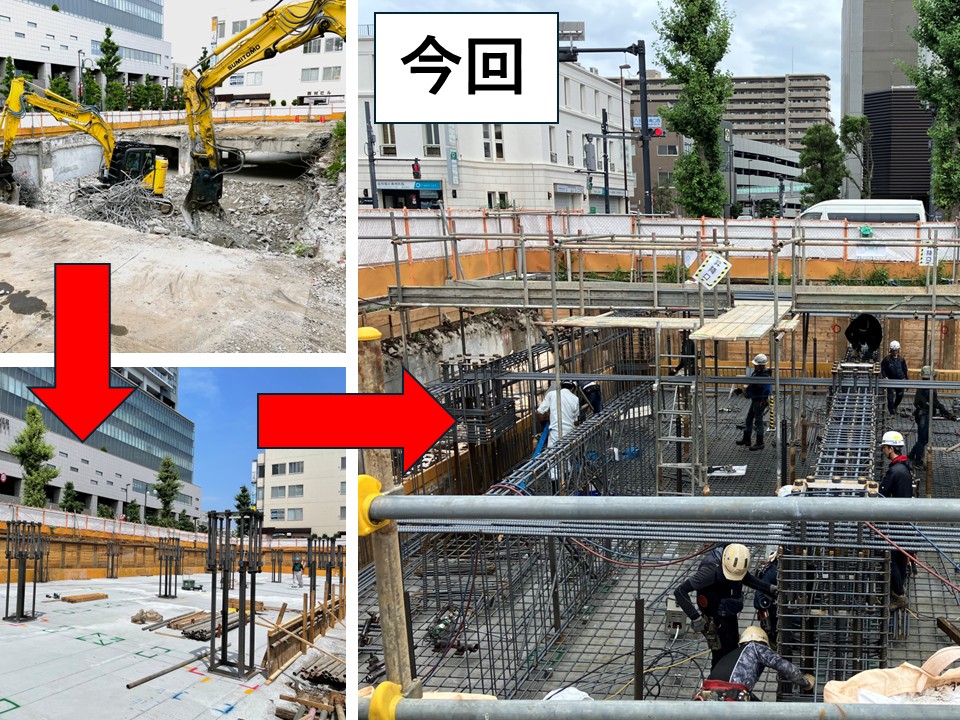
基礎ピットは、基礎の空間を利用し配管や配線を設置するスペースとして使われる部分です。
ピット内に、配管・配線を集めることで、その後の点検や修理作業を容易にし
将来の配管の増加になどにも、柔軟に対応することが可能です。
そんな、基礎ピットの工事を見学していると
基礎の配筋に、大きな穴が開いていることに気が付きました。
これは”人通口”といい、点検や機器の設置の際に
ピット内を、資材や人が通れるようにするための開口だそうです。
しかし、穴をあけると構造的に弱くなってしまうので
強度を補うため、何本もの鉄筋が斜めに入っていることがわかります。
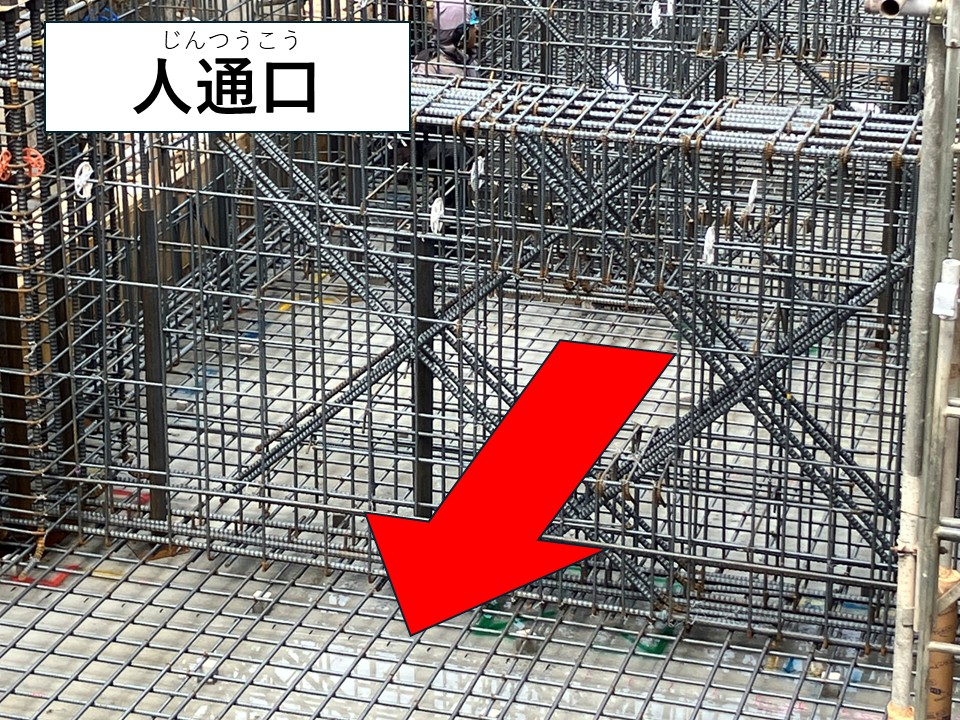
人通口の他にも、鉄筋には配管・配線などを通すための穴である”設備用スリーブ”や
排水のための”連通管”などが設置され、同様に補強配筋が設置されます。
コンクリートが流し込まれる前に、必要なルートを確保しておく必要があるとのこと。
また、側面の鉄筋の中に、鉄筋とは違う太い棒を発見しました。
これは地中梁等の立部主筋を利用して、基礎鉄筋の高さ形状を安定させるものです。
長い鉄筋を内部からも支えているんですね。
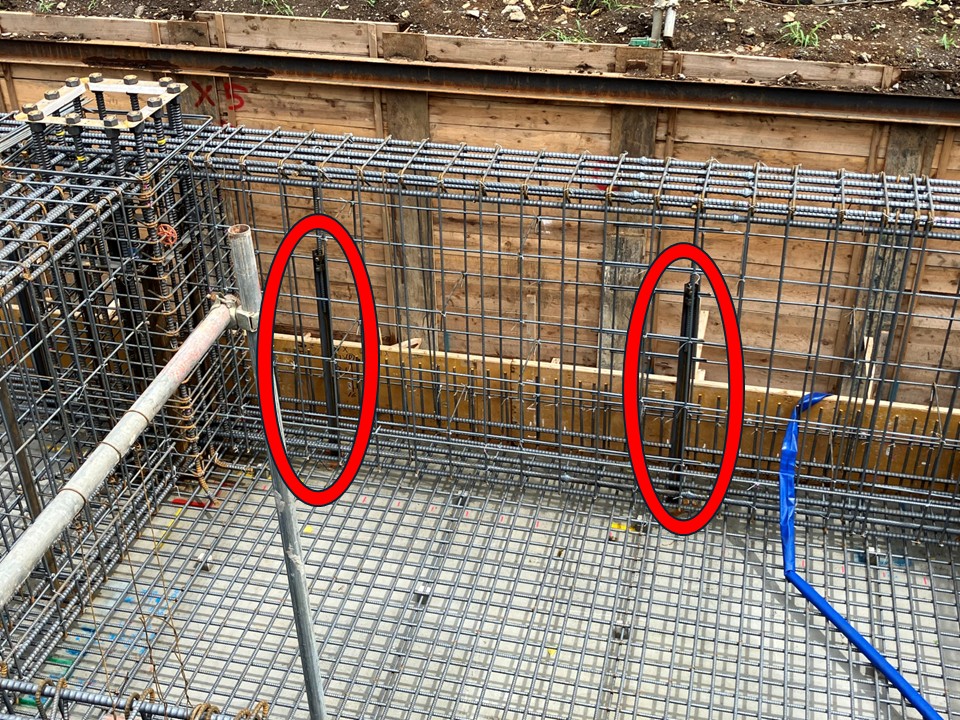
また、このように基礎配筋の工事を進めていく中で、活躍するのが
私が撮影のために歩いている鉄筋足場。
この足場は、資材の運搬や仮置き場として使われ、工事をスムーズに進めるために必要な仮設物です。
そして、この作業足場の設置計画を立てるのも施工管理者の仕事の1つ。
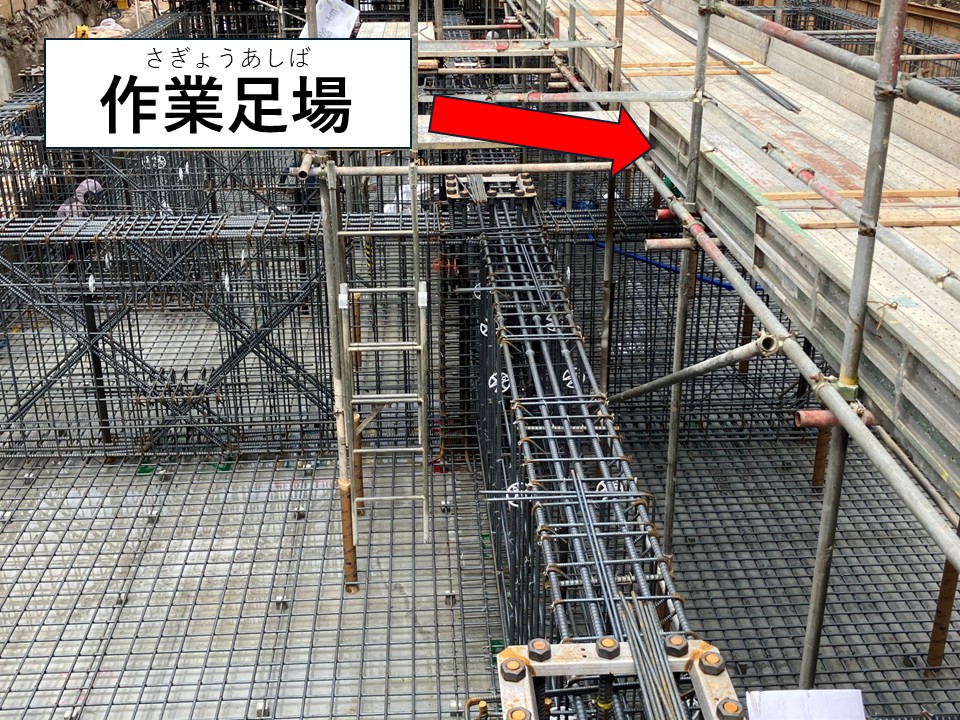
敷地や建物の形状によりますが、基本的に建物の柱に干渉しないような場所に計画します。
また、十字にすることで作業員が通行しやすくなります。
今回の取材では、大勢の職人さんが、縦横無尽に作業を進めている姿が印象的でした。
建物が出来上がってくると、壁や床などで遮蔽されて
現場を見渡すことができなくなるので、このような貴重な体験ができたことが嬉しいです。
2025年9月19日